『鼻』読書感想文の例文【小学生・中学生・高校生】7作品
『鼻』は芥川龍之介の代表作の一つであり、読書感想文の定番本と言えます。『鼻』は扱っているテーマが顔ということでなんとなく取っつきやすく、読書への抵抗感が少ない感想文を書くには大変オススメの小説です。
こちらでは主に、小学校高学年から中学生、高校生が1200字、1600字、2000字程度(原稿用紙で3枚、4枚、5枚程度)で感想文を書くことを想定してアドバイスや読書感想文の例となる見本を掲載しております。
読書感想文の提出には、1200字、2000字以内といった「文字数の規定」があることが多いものですが、文章を書きなれない人には、どうしても文字数が規定の量まで書けない、という人が多いものです。今回はどのジャンルの本にも対応できる文字数調整の方法です。
仮に800字や1000字、1500字といった少ない文字数の読書感想文を書く場合にも「書き方の着眼」の一つとして参考になるかと思いますのでご活用いただければ幸いです。
~~目次~~~~~~~~~~~~~~~
 『鼻/芥川龍之介』あらすじ
『鼻/芥川龍之介』あらすじ
 『鼻』読書感想文【7作品】
『鼻』読書感想文【7作品】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
をご案内いたします。
 『鼻/芥川龍之介』あらすじ
『鼻/芥川龍之介』あらすじ
『鼻』は鼻の長いお坊さんが顔の事をあれこれ言われたり笑われたりして傷つく苦労話です。その悩みっぷりにユニークさを感じる作品ではありますが、お坊さんをバカにする人たちの心理から人のエゴイズムを感じ取れる作品です。中学生・高校生の顔に興味のある年頃ならばこの作品の世界に色々な意見をもって読書感想文に取り組みやすいと言えます。
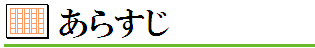
池の尾(現在の京都府宇治市池尾)の僧である禅智内供(ぜんちないぐ)は五、六寸(約15 – 18cm)の長さのある滑稽な鼻を持っているために、人々にからかわれ、陰口を言われていた。内供は内心では自尊心を傷つけられていたが、鼻を気にしていることを人に知られることを恐れて、表面上は気にしない風を装っていた。
ある日、内供は弟子を通じて医者から鼻を短くする方法を知る。内供はその方法を試し、鼻を短くすることに成功する。鼻を短くした内供はもう自分を笑う者はいなくなると思い、自尊心を回復した。しかし、数日後、短くなった鼻を見て笑う者が出始める。内供は初め、自分の顔が変わったせいだと思おうとするが、日増しに笑う人が続出し、鼻が長かった頃よりも馬鹿にされているように感じるようになった。
人間は誰もが他人の不幸に同情する。しかし、その一方で不幸を切り抜けると、他人はそれを物足りなく感じるようになる。さらにいえば、その人を再び同じ不幸に陥れてみたくなり、さらにはその人に敵意さえ抱くようにさえなる。
鼻が短くなって一層笑われるようになった内供は自尊心が傷つけられ、鼻が短くなったことを逆に恨むようになった。
ある夜、内供は鼻がかゆく眠れない夜を過ごしていた。その翌朝に起きると、鼻に懐かしい感触が戻っていた。短かった鼻が元の滑稽な長い鼻に戻っていた。内供はもう自分を笑う者はいなくなると思った。
 『鼻』読書感想文の例文【7作品】
『鼻』読書感想文の例文【7作品】
感想文を紹介する前に、まず、オーソドックスな読書感想文の構成例をご紹介いたします。感想文を書く目的は「この本から何を学んだか」を伝えることです。この点を意識することが重要です。次の順序で書くと読みやすい感想文になります。
これは便利!テキスト入力を原稿用紙に変換できるサイト
 原稿用紙エディター
原稿用紙エディター
 『鼻』を読んで①
『鼻』を読んで①
「鼻」という小説は、実に味わいの深く面白さを持った小説である。何度となく読み返してみても、いつも新鮮で、人間というものについて、考えさせられてしまう。
⇒読書感想文の書き出し例(入賞21パターン)
この小説の中でも、私が特に注目した部分は三つある。一つは禅智内供の自分の鼻に対する心と行動の様子、そして内供を囲むまわりの人々の心が内供の鼻の長さが変わるにつれ、どのように変化したか、最後に、もとの鼻にもどってから内供の暮らしかたの三つである。
第一に、禅智内供の心と行動。内供は、鼻のことをのぞいては、人に恥じるようなところのある人ではない。むしろ、内道場供奉という高い位の僧になっているくらいなのだから、相当に高い教養と人格はそなえていたと思う。
それなのに、内供はなんとかして自分の鼻を短くしようとする。それは、正確に言えば、自分の自尊心をいくりかでも満足しようとしたのだ。そして、ある弟子のおかげで、鼻は短くはなったものの、また、人々に笑われると、もとの鼻になってほしいと願う。内供は、なぜこんなにも、世間の人々の言うことに左右されてしまうのだろうか。
そういえば、私たちの生活にも、そういうものに対するこだわりと、迷いがつきまとう。内供まではいかなくても、私なども、ともすると、人のいうことに自分自身の意志のたいせつさを忘れて、気をとられがちである。内供が、自分自身の感情を見すかされまいとして、とりすましているところなど、現代の人間の行動とそっくりだと思う。
虚栄と自尊心。人間のこの感情は、人間のすべてまでは支配しないとは思うが、少なくとも、現実の生活に対する不満をいだかせはするだろう。そこに、人間の弱さがあるのかも知れない。それに勝つだけの男気と意志を内供がもちあわせていたら、内供はこんな小さなことになやまされなかったであろう。
そんな虚栄と自尊心のために、腹をたてたり、考えこんだりする内供の愚かさは、私には滑稽にみえたが、すぐ後では私も、内供と同じようなことを、日常生活の中でくりかえしていることに気づいて、おそろしくなった。
第二に、周りの人々の心の動きをみていこうと思う。内供の鼻が、人並みはずれて長い時。人々は笑いはするが。ある程度の同情の心で内供をみている。そして、自分が普通の鼻だったことに、心の奥では幸せを感じているに違いない。しかし、内供が鼻を、普通どおりにすると、今度は軽蔑の心で笑ったり、いじわるをするようになる。
人間には、そんな自分勝手な、人の幸福を素直に喜んでやれないようなところもあるのかと、少しおどろいてしまった。なるほど、人間にはそういう「醜さ」があるのかも知れない。すると、内供は、この人々のこういう矛盾した勝手な感情の犠牲者ともいえるわけだ。
しかし、それが事実であろうとも、人間には、信じ合う心としうものがあって、それをうまくカバーしあっているのだ。だから、一方では人間の「醜さ」から目をそらさずにみつめ、一方では人間の信じ合う「美しさ」も認めて生きていけたら、すばらしいと思う。
その点において、この部分は、人間の自分勝手な利己心が現われた例としてみておきたいと思う。そして私は、この小説で、人間の心の一面である「醜さ」を学んでよかったと、嬉しく思っている。
第三に、内供が、この後はどのように暮らしただろうと考えてみた。内供ば、最後に、「こうなれば、もう誰も哂うものはないに違いない」といっている。つまり、内供は、誰も笑う人がいなければ、いささかながらでも幸福だと思うのだ。
しかし、世間の人々の中に、これから必ずしも、内供のその長い鼻を、おかしいと笑う人が現われないとは限らない。いや、きっと現われるだろう。それが人間の世の中であろう。そのとき内供は、また、毎日苦しむことになってしまうだろう。
内供がもし、その鼻のために、自分の品位などがけがされると思い続けているのであったら、このこっけいな話は。内供が死ぬまで、くりかえされていくであろう。私が、そういう内供を軽蔑しながらも、好ましく思えるのは、私にも、内供に似た点があって、共感を呼ぶためなのだろう。不思議な感情である。
この小説は、ほのぼのした面白味があった。人間の「弱さ」や「醜さ」を、そのの中に、さりげなくふくませて、滑稽にそれを表現している。その表現を通して私は、この小説から、人間の自尊心や虚栄や利己的な心を学んだ。同時に、作者も自分のそのような心を、自分で見つめているのかも知れないと思う。そして私は、この「人間」について読みとったものを、これからの私の心の成長の糧としていきたいと思う。
 『鼻』を読んで②
『鼻』を読んで②
この『鼻』という物語は、周囲を気にしすぎて自分を見失ってしまいがちな人間の心の弱さと、噂話や陰口を言う人間の性質をテーマにした作品だった。
⇒読書感想文の書き出し例(入賞21パターン)
人間は周囲の人達が自分をどう見ているのかということに気を使いすぎ、少しでもよく見られたい、褒められたいという気持ちがあるため、しっかりした自分の価値基準を持てない「弱さ」がある。
内供は「だれでも他人の不幸に同情しない者はいない。ところがその人が、その不幸を切りぬけることができると、もう一度そ の不幸におとし入れたくなる。」と言っている。
まさにその通りだとうなずかずにはいられない。私はこの言葉を読んではずかしくなった。そして自分自身 情けなくもなったし、また驚きもした。あまりにも自分のしたこと、思ったことを内供に言い当てられたような気がしたからだ。
私は以前、同級生に授業についてこれない友達がいたので、登校中に先生きどりでよく教えていた。しかし、いつの間にか、その子はだんだん勉強ができるようになってきた。そうなると、今度は私の心がだんだん面白くなくなってきた。
その同級生が難しい問題にも手を上げるようになると、「私が教えたからできるようになったんだ。調子に乗るな。」と心の中で妬むようになったことがあった。
内供の言葉はその時の私の心をピタリと言われたようで恥ずかしさでいっぱいになった。いや私だけでなく人間の心をとてもよく見ているのではないかと感心させられたのだ。
でも、もしかしたら、他人をうらやましく思う心と、相手の幸福を妬む心は人間にとってはしかたのない感情かもしれない。むしろ当然のことなのかも知れない。 しかし、だからといって自分の感情のままに生きていくのもまた心の貧しい人のような気がする。
内供の鼻が弟子の僧の治療によって短くなった時は「これで誰からも笑われなくてすむんだからよかったね」と自分のことのように喜んだ。なのに内供はまたもとのように長い鼻を懐かしがっている。
しかも長い鼻に戻った内供は 気持ちがとても晴ればれとしている。不思議な人間心理であるが、それは内供が「人間は良くも悪くも噂をしたがる生き物であり、気にしだしたら切がない」ということに気づけたのだと思う。そして「気にしないことの大切さ」を悟れたゆえの晴れ晴れとした様子だったのだと思う。
この『鼻』という物語は「他の人の噂に惑わされずに、自分自身をしっかり保つことの大切さ」、言い換えれば「ぶれない心を持つことの大切さ」を私達に教えてくれているのではないだろうか。それと同時に、相手の立場をよく考え思いやりのある言動をとることの大切さを教えようとしていたのではないだろうか。私はこの本の中からそのようなことを学んだ気がする。
「鼻」の感想文の要点部分の例
以下では、「鼻」の感想文の要点の部分(着眼の例)を紹介しています。これらに、導入部分や、最後のまとめ部分を加えれば、学校が求める読みやすい感想文が書けるはずです。
 物語全体を客観的に見た感想の例
物語全体を客観的に見た感想の例
「人は見た目が9割」との定説がある。だいたいは人は第一印象の見た目どおりで間違いないというもので、たしかに表情や顔つきはその人の内面を表しているように感じる。
では「鼻」の禅智内供はどんな人なのだろう?
禅智内供は仮にも仏に使える僧で人に恥じるようなところのある人ではない。高い位の僧というだけあって、高い教養と人格は備えていたハズなのだが、彼の長すぎる鼻に関してのコンプレックスは修行で取り除けるものではなかった。人々も内供の鼻をコソコソと笑い内心では自尊心を傷つけられていた。
ところがある弟子のおかげで悩みの種の鼻を短くすることに成功する。安心したのもつかの間、今度は短くなった鼻を見て更に人々に笑われるのだ。
結局は笑われたくない一心でまた元の鼻になる事を願う。
内供はなぜこんなにも世間の人の言うことに左右されてしまうのだろう?
もし内供の鼻が長くても誰も彼を笑わなかったら?
そもそも、周囲に自分の感情を見透かされたくなくて、取り澄まして過ごしていたこと自体に内供の心の弱さを感じる。
周囲にどのように思われても、それに勝つだけの勇気と意思を持ち合わせていたら、悩むこともなく、自尊心が傷ついたと腹を立てたり、考え込んだりせずに済んだはずだ。
もう一方の周囲の人々も、内供の鼻が長い時は「同情しつつ笑う」態度だが、鼻が短くなったら軽蔑の心や意地悪さで笑い、内供がなぜ鼻を短くしたのか?どんな思いでいたのか誰一人彼の心を思いやる者はいなかった。内供は残酷で矛盾した周囲の人々の醜い感情の犠牲者ともいえるのです。
周囲の悪意ある人々に翻弄され、再び長い鼻にもどった内供は「こうなれば、もう誰も哂うものはないに違いない」と言う。それは今まで笑っていた人間は笑わないとしても、新たに出会う人間が含まれているわけではない。そうなるとまた内供はまた苦しむ事になるのだろうか?
永遠に続く人からバカにされるその鼻の存在がもの悲しく思えた。

 内供への同情と内供が得た教訓が何だったかを語る例
内供への同情と内供が得た教訓が何だったかを語る例
芥川龍之介が現代人の様子を見てどうおもうだろうか?100年以上前に書かれた『鼻』の世界観は当時ユーモラスにあふれた作品だったのだろうか?現代人の自分は『鼻』を読んでとても笑う気持ちになるどころか、なんと残酷な世界観なのだろうとショックを受けたからだ。
顔の中心にある鼻が内供のような大きなものだったら、日々どんな気持ちで暮らしていたことか。まして内供は立派なお坊さんで、宗教感を人に解く仕事をしている自分が鼻の事で悩んでいる姿は誰にも見せられない。でも内心は鼻の話題でビクビクしたり、少しでもマシに見える鼻の角度を研究したりなど涙ぐましい努力をするのだ。
現代では老若男女問わず気軽に美容整形をする時代なわけだが、その悩みの深さを思うと同情せずにおられなかった。今どきはどんな人だってもっと理想の自分になりたいと願い、コンプレックス悟られたくない、治せるものなら治したいと思うのは自分にだって当然あります。
また身近で内供の悲しむ様子を知る弟子や小坊主も同情する気持ちは同じだろう。どこから聞いてきた鼻を短くする方法が功を奏し、人並サイズにやっと落ち着くのだった。
だが人々は今度は鼻を短くしたことをバカにして笑うのだ。
顔が変わったことへの違和感?聖職者のくせに顔に執着した心の愚かさ?を笑ったのだろうか?いやこの時代の人が他人の醜い顔を見て平気で笑うデリカシーのなさは自分たちよりも「内供が下である」との優越感を感じたい心からではないだろうか?笑われる内供よりも彼をバカにした人間は人の自尊心を傷つける事で自分たちの自尊心を高めたい愚かで不幸な人間たちということだと思えてくる。
人間の誇りは誰かから奪って身につけるものではない。でも誇りは誰かに傷つけられる事はある。たかが鼻、されど鼻。元に戻した内供の鼻は「もう哂われない」とは言うが、彼は彼を哂う人々をきっと悲しい思いで見ていたのではないだろうか?「どんな鼻であろうと彼らは笑う対象が欲しかったのだ」と。でもここからやっと鼻の大きさを受け入れて本物の悟りの道を進めるのではないだろうか?

 悪意のある人の心理とそれに負けない心理の持ち方を述べた例
悪意のある人の心理とそれに負けない心理の持ち方を述べた例
人はみんなそれぞれコンプレックスを抱えているものかもしれない。それが他人から見てもわかるものかどうかはさておき、コンプレックスは本人にとっては弱点であり、そこを攻撃されると自尊心に圧倒的なダメージを受けるのでやはり隠し通したいのがコンプレックスなのだ。
だが隠しきれない内供の鼻はさも「なんにも気にしていませんよ」という素振りをしながらも内心びくびくし、不自由な暮らしぶりがユーモアを感じてしまうのが『鼻』なのだ。
内供の鼻のことを知らない者はいない。町のものからは笑われバカにされ、内供の自尊心はズタズタである。自分も顔の事で悩む事はある。ニキビや鼻の黒ずみ、歯並びの悪さなど自分でも見ても憂鬱になるし、悩むのだ。でも内供の悩みは追い詰められたものだった。もう悩んでいるだけじゃなく、積極的にも消極的にもどうにかこの悩みの種をなんとかできないか試行錯誤する。
やっと見つけて鼻を短くできた内供「これでもう哂われることはない」と思ったのに、やはり皆盛んに短くなった鼻をバカにするのだ。
一見してこの周囲のおかしな反応。人間の心には矛盾した二つの感情のせいなのだろう。
人間には他人の不幸に同情するやさしさがある。だがその不幸を切り抜けた他人が必要以上に幸せになることをヨシとしない心理があると思われる。そこにある意地悪な心理は「いつもその人間はやや不幸でいてくれないと物足りない」という薄っすらとした悪意だ。
つまり不幸を抱えたまま幸せになるのは許すが、完全に不幸を超越して得た幸福に不愉快さを感じるのは、自分を超越するのは許さない周囲の人々自尊心からくるのではないだろうか?
芥川龍之介は『鼻』をユニークな小説として書いたのだろうか?この小説から感じとってもらいたいのは「他者のプライドや尊厳を傷つけてはならない」という事。人は心の傷でも命を落とすことがある。自尊心を傷つけると言うのは暴力に等しいとも言えるのだ。
また人の自尊心を傷つける輩は「利己主義の醜さ」を抱えた者なのかもしれない。誰かを犠牲にして自分を立たせるのは、人間は一人で生きていないことの自覚を欠いている事を伝えていると思う。
そしてこの話をユニークにしたのは「自分らしさを受け入れよ」というメッセージからかもしれない。たとえその見た目が世間からバカにされようとも、他人の意見に左右されることはないのである。なぜならばバカにするような他人は自分の意見にも無責任だからだ。世の中の価値観や美の基準が、内供の鼻を美しいものとしたら、バカにしていた人間もすぐに賛美するようになるだろう。ならば自分のコンプレックスを個性と見せるのも自分から発信できるのである。
自分らしさを受け入れる事。顔のニキビや歯並びの悪さを良しとしていいのかは正直難しい。だが、自分のコンプレックスを笑って良いのは自分だけであり、悪意のある意見に負けない心こそが必要なのだと伝えていると思った。
内供が最後に「もう哂われないだろう」と言った言葉から、人間の愚かさをしみじみと感じもう他人に左右されなくなったのだと思った。

 障害への理解を示すことを中心に書く例
障害への理解を示すことを中心に書く例
目の前に鼻の不自由な人がいたら自分はどう接するだろうか?
内供の鼻は長さが五、六寸までとあごの下まで垂れ下がり、形は元も先も同じように太い。実際にそのような人が目の前にいたら、笑うというよりギョッとするのではないだろうか。本来ならば、そんな鼻になった事情があるなら聞いてみたいし、不自由な思いをしていると知れば気の毒に思い、なにか手伝えることがあるなら協力を申し出たいとも思う。個人的には日頃の内供の生活をサポートする弟子の心情に近いものかもしれないので、その巨大な鼻を笑う人々は本当に最低だと思う。
内供自身は何も悪くない、悪くないけどその鼻のせいで周囲の人に気を遣わせる存在であるのは確かだ。彼は日々の生活の不便さやバカにされ自尊心を傷つけられつつ、さも気にしていませんという風を装って懸命に人並の鼻を求めて悩み苦しんでいた。
そんな内供にしたら「その鼻どうしたんですか?」と聞いてくる行為は哂われる事と変わらない羞恥心を感じさせてしまうのだろうか?こちらは友好的な気持ちで理解者でありたいと願っても、彼はその鼻は人とのコミュニケーションを硬直させてしまう代物であった。だから鼻が長い状態でも内供がもう少し弱音や悲しみを口にしてくれていたり、自虐で自らの鼻を話題に出してくれたなら周囲ともっと理解し合えたとも思えるのだ。
だが、内供はもっと積極的に皆に近づく方法を選んだ。皆にとって内供の鼻こそが諸悪の根源なのだから、それがなくなればお互いに気持ち良い関係でいられると思ったのか、ついに内供は鼻を短くすることに成功した。
それなのに内供を知る世間の人々は嘲笑することを辞めなかった。「なんて性格の悪い人々なんだろう」「なぜここで内供を祝福してあげないのだ」と怒りを感じた。だが自分はこの人たちを軽蔑できる立場だろうか?と自分を顧みてみた。
自分は明らかに様子の変な人を笑ったりはしない。だけどそのような人にはなるべく近づかないように距離を取り、関わらない事を心掛ける事があった。なぜならその人に恐怖を感じつつも、どこか見下している自分があり、素知らぬ顔をしならがら遠巻きに興味津々で観察していたような気がするからだ。
こんな自分は笑う人々とそう変わらないのではないだろうか?
今までの自分では内供を気の毒がっても、心は開いてもらえないだろうと思う。それは自分の心のどこかに相手が不幸であることに優越感を感じている自分がいて、その不幸な人を少し幸せにして上げたいという気持ちに驕りがあればきっと受け入れてもらえないと気が付いたのだ。
きっと内供も周囲の人々も自分と世間を比べるから、人をバカにしたり、引け目を感じたりするのだと思う。その中で少しでも優位に立つことが生命保持の安心感を与えるがために本能で劣ったモノをバカにするのかもしれない。
みんなそれぞれ悩みはあるものだ。でも人間には知性があるのだから、もっと人間同士がお互いに尊厳を守ることこそが人間に課せられた課題ではないだろうか

 コンプレックスに負けない生き方・考え方を中心に書く例
コンプレックスに負けない生き方・考え方を中心に書く例
「ワタシは完璧だ」と思っている人間はこの世にどれくらいいるのだろう?
身体的な特徴、性格、頭の良し悪し、お金持ちかどうか、社会的な立場など自分の価値は否応なしにいろんな方面から形づけられるものだ。
本当はこれらでその人間の価値なんか決まるものではないはずなのい、どうしても気にしてしまうのが人間なのかもしれない。
そして自分の悩みに取りつかれると、それは一つ苦労を背負う事になる。他人は実はそんなに人の事は見ていないハズなのだが、気にすれば気にするほど他人が自分の事をじろじろ見て笑ってバカにしているような気がしてくるのである。
内供は鼻を短くして余計に人にバカにされ笑われるようになった。内供にとってはそれが不思議でたまらないのだ。
昔、電車に乗り込んできた異様な雰囲気のおじさんが目につきよく見ると、ほとんど毛のない頭皮に黒い炭で髪があるかのように書き足して黒光りさせている人だった。本人にしたらそれが一番毛髪があるように見えるスタイルなのかもしれないが、どう見ても妙チクリンなのだが本人は大真面目に、ハゲがバレていないと思い込んでいる様子で、可笑しい、気の毒、気味が悪いなど色んな気持ちが沸き起こったことがあった。
この事を思い出してからは、内供という人が鼻が長い時は、いかにも気にしていない素振りが周囲の人々の気に障り、鼻を短くしてからの心の曇りが取れた様子がまた違った苛立ちを周囲に感じさせたのかもしれない。内供は鼻を笑われていたのではなく、鼻を気にして右往左往する内供を笑っていたのだった。
もちろん周囲の人間の方が圧倒的にその人間性に問題があると思う。そんな人間たちとは付き合わなくていいと思う。
ただ人間は一人では生きていけないのだ。どんなに悲しく傷つけられても人間の中で生きていくしかないのだ。もちろん人を平気で傷つける人々とは付き合わなくてもも良いし、相手を選んでいいとは思う。だがどんな状態の自分であってもやはり受け入れてくれる人間同士の繋がりが必要なのだ。
内供は鼻を短くして「理想の自分」に満足し、本当の自分を失いかけた。しかもイライラ怒りっぽくなり、他の僧からの信頼も失ってからはじめて、元の鼻に戻したいと思った。鼻が元に戻る同時に心の持ち方も戻ったことを感じ晴れ晴れしい気持ちになる。
人間は自分の全てに満足する事は出来ないのかもしれない。一つ気になり治しても、次から次へと他にも気になる事ができてしまう。人間にとっての最大の敵は自分自身という言葉もある。
コンプレックスをすべて解消するのは難しい事だと思う。だが自分自身に勝つことが出来れば、ちょっとした悩みなど自分のチャームポイントとして笑って人に話せるのだと思う。「自分は鼻は長いけど、なかなか宗教に関しては詳しいのが特徴」と内供が言う風に、自分を過少評価も過大評価もしない迷わずニュートラルな人になりたいと思った。

読書感想文の書き方のコツ
(テンプレートつき)
書き方の参考用に、過去の入賞作品の紹介ページも作りましたのでご活用ください。



