『ともだち』読書感想文の書き方【例文つき】
2025年の課題図書対策!
こちらでは「第71回 青少年読書感想文全国コンクール」小学校「低学年(1、2年生)」の部
『○○』の「あらすじ(内容)」や「着眼点のポイント」、そして「感想文の書き方の例文」などをご紹介いたします。
※おもに、小学生が800字で読書感想文を書くために「書き方を教える大人むけの内容」になります。

『ともだち』
リンダ・サラ 作 ベンジ・デイヴィス 絵 しらいすみこ 訳
ひさかたチャイルド
1,760円
32ページ
~~目次~~~~~~~~~~~~~~~
 「ともだち」あらすじ
「ともだち」あらすじ
 ここがポイント!着眼点の例
ここがポイント!着眼点の例
 読書感想文の例【例文】
読書感想文の例【例文】
 他の課題図書&過去の入賞作品
他の課題図書&過去の入賞作品
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 「ともだち」あらすじ
「ともだち」あらすじ
主人公の僕とエト君は大の仲良しでした。ある寒い日、二人がいつもの丘に行って遊んでいると、シュー君が来て「なかまにいれてくれる?」といわれたため3人は友達になりました。
シュー君と仲良くなったエト君の様子をみていた僕は、なんだか仲間外れになった気がして少しすねてしまいました。
ある日二人は僕の家に遊びに来ましたが、遊びに出るのを断り、僕は一人でずっと絵をかいて過ごしました。
その後、別の日にまた二人が誘いに来ましたが、こんどは今まで見たことのない大きなダンボールで作った乗り物をもって来ました。
3人は仲良く遊ぶようになり、遊んでいるうちに、僕はシュー君の良いところに気づき始め、3人はとても仲良くなりました。

 「ともだち」着眼点の例
「ともだち」着眼点の例

以下のような着眼点や切り口を参考に話を広げてみるとよいでしょう。
 課題図書4冊の中から、なぜこの本を選んだのかを説明する書き出しもよいでしょう。
課題図書4冊の中から、なぜこの本を選んだのかを説明する書き出しもよいでしょう。
 主人公のぼくは、エト君とシュー君が仲良くしているのを見て、何だか仲間外れになった気がして、嫌な気分になりましたが、その後3人は仲良くなり、シュー君のことも大好きになった様子が描かれていました。この点を深堀して「こういう場合、どうするのが一番いいか」考えたことを感想文に書いてみましょう。
主人公のぼくは、エト君とシュー君が仲良くしているのを見て、何だか仲間外れになった気がして、嫌な気分になりましたが、その後3人は仲良くなり、シュー君のことも大好きになった様子が描かれていました。この点を深堀して「こういう場合、どうするのが一番いいか」考えたことを感想文に書いてみましょう。
 誘いに来た二人でしたが、初め僕に断られてしまいました。しかし別の日に誘いに行ったとき、二人は大きなダンボールで作った車と一緒に僕を誘いに来ましたが、僕はその車に興味を示したことがキッカケで3人はまた仲良くなれましたが、その「誘い方の工夫」を取り上げて感想をかいてみるのもよいでしょう。
誘いに来た二人でしたが、初め僕に断られてしまいました。しかし別の日に誘いに行ったとき、二人は大きなダンボールで作った車と一緒に僕を誘いに来ましたが、僕はその車に興味を示したことがキッカケで3人はまた仲良くなれましたが、その「誘い方の工夫」を取り上げて感想をかいてみるのもよいでしょう。
 自分にも同じようなことがなかったか思い出し「自分も主人公の僕と同じような経験があったこと」を述べ、その時の思い出と、この本の主人公を対比させた感想文にしてみましょう。
自分にも同じようなことがなかったか思い出し「自分も主人公の僕と同じような経験があったこと」を述べ、その時の思い出と、この本の主人公を対比させた感想文にしてみましょう。
 自分にも仲良しの友だちがいる場合、新しい友達ができたのなら、その子とばかり遊んでしまうと、今までのお友達は、この本の主人公とおなじような悲しい思いをしてしまうかもしれません。このことを取り上げ「今までの友だちの気持ちも考えてあげることの大切さを学んだこと」を中心に感想文にまとめるのもよいでしょう。この点にはなかなか気が付きませんから、高得点が期待できます。
自分にも仲良しの友だちがいる場合、新しい友達ができたのなら、その子とばかり遊んでしまうと、今までのお友達は、この本の主人公とおなじような悲しい思いをしてしまうかもしれません。このことを取り上げ「今までの友だちの気持ちも考えてあげることの大切さを学んだこと」を中心に感想文にまとめるのもよいでしょう。この点にはなかなか気が付きませんから、高得点が期待できます。
—–話の広げ方の例———————-
 「この本の内容をお父さんに話すと、お父さんは・・・」というように、家族に本の内容を伝えた際のエピソードを加える感想文もよいでしょう。家族の意見を加えることで、意外性のある感想文や高度な感想文に進展させることができます。
「この本の内容をお父さんに話すと、お父さんは・・・」というように、家族に本の内容を伝えた際のエピソードを加える感想文もよいでしょう。家族の意見を加えることで、意外性のある感想文や高度な感想文に進展させることができます。
例)本の内容をお父さんに教えると、お父さんは「友達とケンカしても、後でまた仲良くなれるように傷つくようなことは言っちゃダメなんだよ」といいました。それを聞いて、私は「なるほど」と思いました。なぜなら、この本のぼくも悪口は言わなかったからすぐにまた遊びに誘われたんだなと思ったからです。・・・など。
 この本にもし「続き」があるなら、どんな内容が書いてあるといいなと思ったかを発表する感想文もよいでしょう。
この本にもし「続き」があるなら、どんな内容が書いてあるといいなと思ったかを発表する感想文もよいでしょう。
 「この本をきっかけにして、いろいろなことを本を読んでもっと勉強したいと思えるようになりました。」・・・という締めくくり方もよいでしょう。読書の習慣を身に着けるキッカケになったとする感想文は「教育的効果の表れを感じさせる感想文」です。
「この本をきっかけにして、いろいろなことを本を読んでもっと勉強したいと思えるようになりました。」・・・という締めくくり方もよいでしょう。読書の習慣を身に着けるキッカケになったとする感想文は「教育的効果の表れを感じさせる感想文」です。
 この本を読んで、物語や経験などを「伝えることの価値」「書き残すことの価値」について気づけたことを発表する感想文も素晴らしい着眼です。そして「自分も大人になったら物語や経験を本に書き残せるような大人になりたいなと思いました。」とするまとめ方も良いでしょう。
この本を読んで、物語や経験などを「伝えることの価値」「書き残すことの価値」について気づけたことを発表する感想文も素晴らしい着眼です。そして「自分も大人になったら物語や経験を本に書き残せるような大人になりたいなと思いました。」とするまとめ方も良いでしょう。
・・・これらの中からいくつかを取り上げ、関連する「自分の思い出」や「最近の出来事」などと絡めて感想文を書いてみましょう。
学校などの教育機関が与える課題は「教育的成果」を期待してのものです。そのため、教育機関からの課題としての読書感想文を書くにあたっては「どのような学びを得ることができたか」を感じ取れる感想文にすることが大切です。つまり・・・
 この本を読んだ後「人として大切なことについて感じ取れた様子」や、「考え方の変化(成長)があった様子」、これらが文章から伝わってくる内容の感想文を書くことが特に大切となります。
この本を読んだ後「人として大切なことについて感じ取れた様子」や、「考え方の変化(成長)があった様子」、これらが文章から伝わってくる内容の感想文を書くことが特に大切となります。
 直接的な書き方の例としては「この本を読んで、これからは、もっと○○○○○を○○○○○しようと思うようになりました。」といった「心の変化を伝える一文」を入れると出題意図に合致した感想文になります。
直接的な書き方の例としては「この本を読んで、これからは、もっと○○○○○を○○○○○しようと思うようになりました。」といった「心の変化を伝える一文」を入れると出題意図に合致した感想文になります。
 また、小学生の場合「優しさ」「思いやり」「正直さ」「公平性」「努力」「勇気」・・といった人間にとって大切なことについて、その大切さを理解できた様子が読み取れる内容にすることが大切です。
また、小学生の場合「優しさ」「思いやり」「正直さ」「公平性」「努力」「勇気」・・といった人間にとって大切なことについて、その大切さを理解できた様子が読み取れる内容にすることが大切です。
 「ともだち」読書感想文の例【例文】
「ともだち」読書感想文の例【例文】
以下に3作品をご紹介いたします。文字数はまちまちですが「書き方」や「着眼点」の参考にしていただければと思います。学年によってはまだ習っていない漢字も含まれている場合もあるため、その部分も修正したあとの文字数で、規定の文字数に合わせてください。
※原稿用紙に書く際は、改行のための空白部分も字数として数えます。句読点はそれぞれ1字に数えます。また、題名、学校名、氏名は字数に数えません。
これは便利!テキスト入力を原稿用紙に変換できるサイト
 原稿用紙エディター
原稿用紙エディター

![]() 「ともだち」を読んで①
「ともだち」を読んで①
ぼくは、絵本『ともだち』をよみました。えらんだりゆうは、ともだちと外で遊んでいるようすのひょうしがきになったからです。
「ぼく」は、エトくんというともだちと、いつもいっしょにあそんでいました。でも、ある日、シューくんが「いっしょにあそぼう」といってきて、エトくんはすぐにシューくんと仲よくなります。ぼくはそれを見て、なんだかさびしくなってしまいました。「ぼく」がすねているところを見て、ぼくもおなじようなことがあったなと思い出しました。
じっさいに、ぼくもなかよしのともだちが、ほかの子とばかりあそんでいるのを見て、さびしいきもちになったことがあります。さそわれても、すなおに「うん」といえなくて、一人でべつのことをしてしまったこともありました。
でも、このえほんをよんで、たいせつなことに気づきました。「ぼく」は、エトくんやシューくんに、いやなことを言ったり、わるくちを言ったりしませんでした。だから、ふたりはまた「いっしょにあそぼう」とさそいにきてくれて、三人でたのしくあそべるようになったのです。
とくにすてきだなと思ったのは、シューくんが、大きなダンボールでつくったのりものをもってきたところです。それがきっかけで、「ぼく」もシューくんとあそんでみたくなり、シューくんのやさしいところや、おもしろいところを見つけることができました。
この本をよんで、ぼくは「ともだちがふえるって、さびしいことじゃないんだな」と思いました。あたらしいともだちとあそぶことで、もっともっとたのしいことがふえるんだと知りました。そして、じぶんのきもちにすなおになりながらも、ともだちをたいせつにすることが、いちばん大事だと思いました。
これから、もしまたさびしいきもちになったときは、「いっしょにあそぼう」ってすなおに言えるようにがんばりたいです。『ともだち』は、そんな大切なことをおしえてくれる、やさしいえほんでした。

![]() 「ともだち」を読んで②
「ともだち」を読んで②
この本をよんで、ぼくは「なんだか じぶんみたいだな」と思いました。『ともだち』というおはなしは、「ぼく」と エトくんと シューくんという 三人のともだちのことが かいてあります。
はじめ、「ぼく」と エトくんは いつもいっしょに あそんでいる なかよしでした。でも ある日、シューくんが「なかまにいれて」とやってきます。エトくんは すぐにシューくんと なかよくなって、三人であそぶようになります。
それを見た「ぼく」は、すこし さびしくなってしまいます。じぶんだけ、なかまはずれに なったようなきがして、あそぼうとさそわれても、「うん」とは いえませんでした。ひとりで えをかいて すごしている「ぼく」のきもちは、ぼくも よくわかります。
でも、エトくんとシューくんは あきらめませんでした。ある日、大きなダンボールの くるまを つくって、また「いっしょにあそぼう」ときてくれました。そのくるまが おもしろそうだったので、「ぼく」はまた いっしょにあそぶようになります。
ぼくは、「さそいかたを くふうする」ことって 大じなんだなと思いました。ことばだけじゃなくて、「これであそびたい」と思うような ものを もってきてくれたことが、とてもうれしかったんだと思います。
この本をよんで、「ともだちの気もちをかんがえること」が大じだとわかりました。あたらしいともだちができても、まえからのともだちのことも わすれないで、みんなが たのしくすごせるようにしたいです。
ぼくも、これから ともだちの気もちを 大じにできるように なりたいと思いました。

![]() 「ともだち」を読んで③
「ともだち」を読んで③
ぼくは、『ともだち』という絵本をよみました。この本のなかで、「ぼく」とエトくんは、とってもなかよしでした。でも、ある日、シューくんが「いれて」といってきて、エトくんがすぐにシューくんとあそぶようになりました。それを見た「ぼく」は、ちょっぴりさびしくなって、すねてしまいます。
ふたりがあそびにきても、「ぼく」は、あそににはいかず、へやでひとりでおえかきをしていました。そんなとき、エトくんとシューくんが、べつの日に大きなダンボールののりものをもって、また「ぼく」をさそいにきてくれました。
ぼくは、そのダンボールのくるまにきょうみをもちました。そして、三人でまたいっしょにあそべるようになりました。
このとき、ぼくはエトくんとシューくんが、すごくやさしくてすごいな、と思いました。なぜなら、たぶん二人は「どうしたらあそんでくれるかな?」って、いろいろかんがえてくれたんじゃないかなと思ったからです。
じぶんのことをおもい出してみたら、ぼくも、むかしあたらしいおともだちがきたときに、ちょっとさびしいきもちになったことがありました。でも、その子がもってきためずらしいカードゲームをきっかけに、いっしょにあそべるようになって、なかよしになれました。
この本をよんで、ぼくはおともだちをたいせつにするには、あいてのきもちをかんがえてあげることが大じだとわかりました。あたらしいともだちがふえても、まえからのともだちのことも大じにすることが、もっと大切なんだと思いました。
また、行どうやことばで気もちをつたえるって、すてきなことだなと思いました。ぼくも、だれかがさびしそうにしていたら、「いっしょにあそぼう」って、やさしくさそえる子になりたいです。
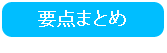
みんなが仲良くいられる考えかたの大切さ
用紙・字数のルール その他
原稿用紙を使用し、縦書きで自筆してください。原稿用紙の大きさ、字詰に規定はありません。
文字数については下記のとおりです。
小学校低学年の部(1、2年生) 本文 800字以内
小学校中学年の部(3、4年生) 本文1,200字以内
小学校高学年の部(5、6年生) 本文1,200字以内
中学校の部 本文2,000字以内
高等学校の部 本文2,000字以内
※句読点はそれぞれ1字に数えます。改行のための空白か所は字数として数えます。
※題名、学校名、氏名は字数に数えません。
応募のルールについての詳細は主催者ページで発表されます。
⇒ 「青少年読書感想文全国コンクール応募要項」
 他の課題図書&過去の課題図書と入賞作品
他の課題図書&過去の課題図書と入賞作品
2025年の小学校低学年(1,2年生)用の課題図書は次の4冊です。
クリックすると解説ページが開きます。

過去の課題図書の紹介
過去の課題図書も「自由読書」のジャンルとして感想文を提出することができます。そのため、どの本を読もうか迷っている場合「書き方のアドバイス」や「例文」が存在する過去の課題図書の中から本を探してみるのも得策です。
また、長年読み継がれている「名作」の中から感想文を書く本を選ぶのもよいでしょう。こちらも書き方のアドバイスや例文つきです。
 名作おすすめ本一覧
名作おすすめ本一覧
書き方の参考用に、過去の入賞作品の紹介ページも作りましたのでご活用ください。

読書感想文の書き方のコツ
(テンプレートつき)




